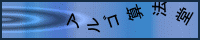
| 半音 | 度数 | 周波数比 |
|---|
平均律の計算法を紹介します。
平均律というのは、1オクターブを12に均等に分割することです。1オクターブの周波数比は2ですから、半音の音程は2/12としたいところですが、そう単純ではありません。
というのは、音程は周波数の比率で決まります。半音の周波数比を x とすれば、ある音(周波数 f )の半音上の音の周波数は、f*x。すると全音上はそのさらに半音上ですから、 (f*x)*x となります。
このようにして、半音を1オクターブ分を積み重ねると、 f*(x12)ということになります。他方、オクターブ上は周波数が2倍になるので、2*f 。そこで、半音を計算するための式は、
これを解くと、半音の周波数比は、21/12(= )となります。半音上の音は、およそ6%周波数が高いことになります。
半音 n 個高い音の周波数比は、
となります。これを実際に計算した結果を半音周波数比表にまとめました。
音程差は比率なので、通常ならば乗算(除算)で計算しますが、対数(log)を取るとその値は加減算で計算できます。このとき、1オクターブが1200、つまり、半音が100となるように決めた単位が centで、音程を論じるときには、この値がよく用いられます。周波数比(r)と cent 値 (n) の関係式は次のとおりです。
平均律の音程のうち、純正音程とのずれが問題になる長三度と完全五度について、そのずれのcent値を求めてみます。
まず、長三度の場合です。
周波数波比は、平均律:24/12 = 、純正律:5/4です。これから、二つの音程の比を取り、centに換算すると、
となり、音程差は半音の1/10強だけ平均律の方が高くなっています。ギターをチューニングするとき、3弦と2弦をハーモニックスで合わせたり、気持ちのいい響きで合わせると、純正音程になるので、それより、ちょっと高めにしないと平均律には合いません。
次に五度の場合です。
周波数波比は、平均律:27/12 = 、純正律:3/2です。これから、二つの音程の比を取り、centに換算すると、
となり、平均律の方がわずかに低いことになります。
音の高さを周波数で決めるものです。現在は、基準値としてA=440Hz が広く用いられています。しかし、これは、何らかの音楽的な理由で決められたものではなく、また、決められた時期も20世紀になってからです。それ以前には、各国、あるいは各地でさまざま基準音高が使われていました。
左の表は、A=440Hz の各音の絶対音高を表しますが、基準周波数の欄に別の値たとえば、435などを入れて「再計算」ボタンを押すと、それに応じて計算しなおします。
表を見れば、楽器の音の周波数(Hz)を知ることができます。例えばギターならば、
| 1E: | 329.6275569128699 |
| 2B: | 246.94165062806206 |
| 3G: | 195.99771799087463 |
| 4D: | 146.8323839587038 |
| 5A: | 110 |
| 6E: | 82.4068892282175 |
ベースならば、次のとおりです。
| 1G: | 97.99885899543733 |
| 2D: | 73.41619197935188 |
| 3A: | 55 |
| 4E: | 41.20344461410875 |
バイオリン=マンドリンでは、
| 1E: | 659.2551138257398 |
| 2A: | 440 |
| 3D: | 293.6647679174076 |
| 4G: | 195.99771799087463 |
となります。