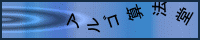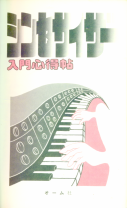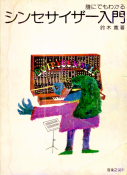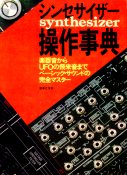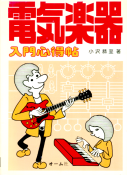|
ミュージック
シンセサイザー入門
|
| 白砂昭一・立花昭嘉・三枝文夫 | オーム社 | --- | 1977
|
| 1章 ミュージックシンセサイザーとは
| | 1-1 ミュージックシンセサイザーという用語
| | 1-2 ミュージックシンセサイザーの生まれた背景
| | 1-3 オールソンの RCA ミュージックシンセサイザー
| | 1-4 最近の市販のミュージックシンセサイザー
| | 2章 シンセサイザーの原理と構成
| | 2-1 電子楽器の音
| | 2-2 人間の聴音機構とシンセサイザー
| | 2-3 音の時間的変化
| | 2-4 電圧制御とはどういうことか
| | 2-5 シンセサイザーの構成
| | 2-6 人間とのインターフェース
| | 2-7 パネル上の信号の流れ
| | 2-8 各機能ブロックの働き
| | 3章 シンセサイザーで何ができるか
| | 3-1 現実に即した使い方
| | 3-2 効果音あれこれ
| | 3-3 タイプによる使いかっての違い
| | 3-4 イメージの確認という音作り
| | 3-5 シンセサイザーも楽器である
| | 3-6 実験的な使い方[1]
―ソルフェージュの学習に利用
| | 3-7 実験的な使い方[2]
―従来の楽器の分析的学習に利用
| | 3-8 実験的な使い方[3]
―作曲の研究への利用
| | 4章 リアルタイム演奏技法
| | 4-1 ライブタイムシンセサイザー
| | 4-2 マルチキーボードプレイ
| | 4-3 シンフォナイザー
| | 4-4 再生上の注意
| | 4-5 PAとの関連
| | 5章 多重録音技法
| | 5-1 再生音楽
| | 5-2 一般的な方法
| | 5-3 本格的多重録音
| | 5-4 オーケストレーション
| | 5-5 シンセサイザー雑感
| | 6章 シンセサイザーの応用
| | 6-1 回路網をシステムアップするときの注意
| | 6-2 扱いで必ず気をつけたいこと
| | 6-3 機能を拡大させる
| | 6-4 種々の機能回路を考える
| | 7章 各種シンセサイザーの特徴と将来
| | 7-1 パフォーマンスシンセサイザー
| | 7-2 システムシンセサイザー
| | 7-3 多声シンセサイザー
| | 7-4 その他のシンセサイザー
| | 付録 シンセサイザー用語解説
|
|
|
アナログシンセサイザー全般に関するおおまかな解説といった内容の本です。
まずは、当時の最新の状況を概観しようというのが狙いでしょう。
この本を読んだからといって、使いこなしや、音色作りに、即、取り掛かれるという内容ではありません。
この次に紹介する「続。。。。」とペアになっています。
(2005/03/23)
|

内扉です |
続 ミュージック
シンセサイザー入門
|
| 和田則彦・三枝文夫 | オーム社 | --- | 1979
|
| Ⅰ.ハード編
| | 1章 シンセサイザーの回路構成
| | 1-1 はじめに
| | 1-2 電子回路からみたシンセサイザーの各機能
| | 1-3 シンセサイザーに使用される部品
| | 1-4 電圧制御発振器(VCO)
| | 1-5 電圧制御フィルター(VCF)
| | 1-6 電圧制御増幅器(VCA)
| | 1-7 包絡線発生器
| | 1-8 その他の付属回路
| | 2章 シンセサイザーの周辺機能と周辺機器
| | 2-1 シンセサイザーと周辺機器
| | 2-2 外部楽音信号を処理する機能
| | 2-3 プログラム機能について
| | 2-4 ギターシンセサイザー
| | 2-5 ボコーダー
| | 2-6 シーケンサー
| | 2-7 エコーおよびリバーブレーション装置
| | 2-8 イコライザ
| | 2-9 オシロスコープ
| | 2-10 チューナー
| | 2-11 マルチメーター
| | 3章 シンセサイザーとコンピュータ制御のしくみ
| | 3-1 ディジタル技術の楽音合成への利用
| | 3-2 ディジタル式波形合成法
| | 3-3 ディジタル計算機を用いた音楽合成プログラム
| | 3-4 電圧制御型シンセサイザーとディジタル計算機の接続
| | 3-5 マイクロコンピュータ制御によるシンセサイザー
| | 4章 ディジタルシンセサイザーとシンセサイザーの将来
| | 4-1 ディジタルシンセサイザー
| | 4-2 ポリフォニック・アナログシンセサイザー
| | 4-3 ハイブリッドシンセサイザー
| | 4-4 シンセサイザーの将来
| | Ⅱ.ソフト編
| 5章 多重録音技法の実際[Ⅰ]
サウンドクリエータ側の制作法
| | 5-1 ミュージックシンセサイザーと録音
| | 5-2 多重録音の方法
| | 5-3 サイマルシンクレコーディング
| | 5-4 ハイブリッドシンセサイザー
| | 5-5 VCAを用いたコンピューティングミキシング
| 6章 多重録音技法の実際[Ⅱ]
レコード制作者からの評価
| | 6-1 シンセサイザーによる音楽
| | 6-2 レコード音楽とは
| | 6-3 シンセサイザーのレコードを作ろうと思ったら
| | 6-4 カッティング処理上の問題点
| | 7章 作曲・実験音楽の実時間演奏技法の実際
| | 7-1 実時間演奏とは?
| | 7-2 実時間合奏のための準備
| | 7-3 実時間合奏の実際とハードウェア的問題点
| | 7-4 実時間合奏の実際とソフトドウェア的問題点
| | 7-5 シンセサイザー実時間演奏と他メディアとのシンクロについて
| | 8章 音楽教育におけるシンセサイザーの活用
| | 8-1 学校教育での使用
| | 8-2 学習用エチュードの製作
| | 8-3 音響制作回路構成表示法
| | 8-4 エチュードの例
| | 8-5 監視系の重要性
| | 9章 CM・テーマ・劇伴音楽におけるシンセサイザーの活用
| | 9-1 コマーシャルベースの音楽
| | 9-2 シンセサイザー導入によるメリット
| | 9-3 シンセサイザーを使う具体的知識
| | 9-4 新しい手法と将来
| | 付録[Ⅰ] 楽器音のディジタル分析について
| | 付録[Ⅱ] シンセサイザー作品テープコンテスト必勝法
| | 付録[Ⅲ] シンセサイザーのレコード一覧
|
|
|
前項の書籍とペアになっている、上下で言えば下巻に相当します。
上巻が概論、下巻が各論といった趣です。
大まかに、ハード編、ソフト編に分かれており、
ハード編が実質的なアナログシンセサイザー入門といったところです。
ハード編は、特別詳しく書かれているわけではないのですが、動作の考え方、回路構成など、
今、読み返してみても興味深い内容です。
ソフト編は、当時ですから、
マルチトラックのテープレコーダーを使った多重録音に重点が置かれています。
分量が多いにも関わらず、それほど、内容が濃いという印象は持てませんでした。
(2005/03/23)
|
 |
ミュージック
シンセサイザーの実験と工作
|
| 白砂昭一 | オーム社 | --- | 1979
|
| 1章 試作シンセサイザーの構成
| | 1-1 取り上げている機能回路の種類
| | 1-2 4種のシリーズについて
| | 1-3 モジュール化について
| | 1-4 ケースのデザインについて
| | 1-5 試作しようとする人へ
| | 2章 回路を構成する素子とその働き
| | 2-1 抵抗
| | 2-2 静電容量(キャパシタンス)
| | 2-3 電磁誘導(リアクタンス)
| | 2-4 ダイオード
| | 2-5 トランジスタ
| | 2-6 電界効果トランジスタ
| | 2-7 集積回路
| | 2-8 オペアンプ
| | 2-9 製作に必要な部品一覧
| | 3章 工作に際して
| | 3-1 工作を始める前に
| | 3-2 工作に必要な道具類と材料について
| | 3-3 調整について
| | 3-4 調整に必要な計測機器類について
| | 4章 機能モジュールの製作法
| | 4-0 電源
| | 4-1 ウィーンブリッジ発振器
| | 4-2 M-095 並列信号分配器と入出力コネクター変換器
| | 4-3 M-110 8チャンネルミキサー
| | 4-4 M-201 4チャンネル交直両用ミキサー
| | 4-5 M-101 電圧制御式増幅器
| | 4-6 M-205 電圧制御式増幅器(交直両用)
| | 4-7 M-140 リング変調器
| | 4-8 M-105 エンベロープジェネレーター(AR型)
| | 4-9 M-225 エンベロープジェネレーター(ADSR型)
| | 4-10 M-147 トリガー遅延器(2連)
| | 4-11 M-248 ゲート遅延器
| | 4-12 M-115 電圧制御式く形波発生器
| | 4-13 M-125 電圧制御式正弦波-のこぎり波発生器
| | 4-14 M-120 指触式鍵盤
| | 4-15 M-192 操縦棹式四重制御電圧源
| | 4-16 M-130 制御電圧処理器
| | 4-17 M-135 ノイズ発生器
| | 4-18 M-117 電圧制御式発振器
| | 4-19 M-180 鍵盤
| | 4-20 M-260 電圧制御式低域通過フィルター
| | 4-21 M-265A 電圧制御式高域通過フィルター
| | 4-22 M-265B フィルター結合回路部
| | 4-23 M-215 電圧制御式発振器(可聴周波および超低周波)
| | 4-24 M-145 タイミングパルス発生器
| | 4-25 M-150 継時的制御電圧発生器
| | 4-26 M-170 エンベロープフォロア
|
|
|
モジュール式のアナログシンセを自作するのがテーマです。電源から始まり、
目次の通りの沢山のモジュールを製作することになります。
パネル加工から、回路図、エッチングパターンまで、すべてが書かれているので、
自作派にはうれしい本だと思います。
こういう本が出版されていたことが素晴らしいです。
ただし、私自身がこれに沿って製作した事がないので、
出来上がりのシンセサイザー自体については、何も書くことができないのが残念です。
(2005/03/23)
|
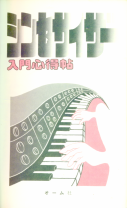
内扉です |
シンセサイザー
入門心得帖
|
| 山口公典・新美幸二 | オーム社 | --- | 1977
|
| 第1章 | シンセサイザーとは何か
- シンセサイザーという言葉の意味
シンセサイザーとアナライザー/波形と振幅エンベロープ/シンセサイザーの基本構成/電子オルガンとの違い
- シンセサイザーの生まれた背景
電子回路による発音/テルミンとオンドマルトーノ/ハモンドオルガンと電気ピアノ
- いろいろなシンセサイザーの出現
オルソンのシンセサイザー/電圧制御型シンセサイザー/シンセサイザーとしてのデジタル計算機/MUSIC V/GROOVE/ディジタルシンセサイザー
| | 第2章 | シンセサイザーのための音響知識
- 音の性質
音波/音圧/周波数とピッチ/位相/波形とスペクトル
- 楽器音の性質
楽音と雑音/楽器音と雑音のスペクトル/楽器音と雑音の音圧レベル/ビブラート,トレモロ,ポルタメント/楽器音の立ち上がりと減衰
- いろいろな楽器音
エレクトーン/電圧制御型シンセサイザー/アコースティックギター/管楽器/弦楽器/打楽器/人声
- 幾つかの大切な音楽用語
音階/音名/楽器音の基本周波数範囲
| | 第3章 | シンセサイザーの原理と働き
- シンセサイザーの構成
シンセサイザーに必要なもの
- いろいろな波形発生方法
波形記憶法/正弦波加算法/フィルター法/変調法
- 音を操縦する
変動の付け方/ADSR発生器とLFO/手動による変化
- 電圧制御型シンセサイザー
VCO-音の素材1-/ノイズジェネレーター-音の素材2-/VCF-音の加工1-/固定フィルター-音の加工2-/VCA-音の加工3-/エンベロープジェネレーター-変化の源1-/LFO-変化の源2-/キーボード(KB)-これも一つの信号発生器-/コンソールパネル-シンセサイザーの顔-
| | 第4章 | シンセサイザー・ア・ラ・カルト
- システムシンセサイザー
MOOG SYSTEM55/いろいろなシステムシンセ/システムシンセによる音作り
- コンボシンセサイザー(モノフォニックシンセサイザー)
YAMAHA CS-10/MINIMOOG/ROLAND SH-3A
- プリセットシンセサイザー
シンセサイザーを使った音のカンズメ/KORG MICRO PRESET/ROLAND SH-200
- ポリフォニックシンセサイザー
演奏効果の高いシンセサイザー/KORG 800DV/POLY MOOG/YAMAHA GX-1/電子オルガン
- その他のシンセサイザー
ギターシンセサイザー/パーカッションシンセサイザー
- 付加装置
シーケンサー/サンプル&ホールド/音響効果装置
| | 第5章 | シンセサイザーの「演奏」
- 音作りの基礎
音のイメージ/音の合成と分析/音出し
- 音作りの具体例
ピアノ音/バイオリン音/トランペット音/波の音・風の音/猫の話し声/マンボーの大あくび/UFO大接近/波形は音の素材
- 多重録音技法
多重録音技法の特徴/多重録音とは/マルチチャンネル録音技法/オンマイク録音/多重録音の実際/サイマルシンク録音
- ライブ演奏
実時間演奏の音作り/各種楽器との並用
| | 第6章 | これからのシンセサイザー
普及するシンセサイザー/変ぼうする音楽
- マイコン付きシンセサイザー
自動演奏できるシンセサイザー/マイコン組込みの一例/ハイブリッドシンセサイザー
- ディジタルシンセサイザー
楽音合成の担い手/サムソン・ボックス/アレスのシンセサイザー/Synclavier/時分割多重化/重要な楽器としての質
- シンセサイザーとオーディオ
音自体の味わい/コンボからコンポへ
|
|
|
マンガのイラスト入りで、かなり、見た目はかなりライトタッチですが、内容は充実しています。
「入門心得帖」という泥臭い書名とは、かけ離れており、読みやすく、
アナログシンセに関しての一通りの知識を得ることができます。
さすがに、回路までは触れられていませんが、一般的な話はこれで十分だと思います。
YAMAHAのCS-10を題材にして、いくつか、具体的な音づくりをしている章があります
(パッチシート掲載)。
(2005/03/23)
|
 |
シンセサイザーのたのしみ
|
| 菊地公一 | 日本放送出版協会 | --- | 1978
|
1章 シンセサイザーの面白さ
- 不思議な「音色創造器」
- (1) 今までの楽器とはまったく違った音楽の道具
- (2) 手始めに,誰でも知っている楽器の音を
- (3) 自然音などの描写で情景の演出を
- (4) 空想の音,イメージの音でオリジナルなサウンドを
- シンセサイザーで楽しもう
- (1) 電子オルガンに加えて聞き手を魅了
- (2) シンセサイザーでアンサンブル
- (3) 多重録音でひとりのオーケストラ
- (4) 多重録音の応用でサウンド・ドラマ,音の詩集の制作
- (5) 思い出を音で残すサウンド・コラージュ
- (6) シンセサイザー・カラオケで歌手の気分
- (7) ビデオや8ミリ映画のサウンドトラック制作
- (8) 演劇部の舞台では万能音響装置
- (9) アイデアで広がるシンセサイザーの楽しみ
2章 シンセサイザーの音づくり
- シンセサイザーの仕組み
- (1) シンセサイザーの発想は?
- (2) 音の要素を整理してみると
- (3) 電気じかけの振動源
- (4) 細かい振動をふるいにかけて音づくり
- (5) 振動を,音の出方,消え方に従って拡大
- (6) シンセサイザーの基本的な仕組み
- 楽器音の音づくり
- (1) ピアノの音をシンセサイザーで
- (2) 同じ手順でクラリネットの音づくり
- (3) 他の要素も加えてバイオリンの音づくり
- 効果音,特殊音の音づくり
- (1) 波の音で浜辺の情景をつくろう
- (2) 音色効果を駆使した風の音
- (3) 素材をそのまま生かしてUFOの飛行音
- (4) 各回路の応用でさまざまな音づくり
- 音づくりの素材を見つめなおしてみよう
- (1) 各回路を流れる信号の区別
- (2) オーディオ信号にも範囲がある
- (3) VCOのチューニングとは
- (4) 音づくりの発展性
3章 シンセサイザーの種類と周辺機器
- シンセサイザーのいろいろなタイプ
- (1) 鍵盤を備えたシンセサイザー
- (2) 鍵盤以外のもので演奏するシンセサイザー
- (3) シンセサイザーの鍵盤に代わるもの
- シンセサイザーの周辺機器
- (1) シンセサイザーを鳴らすためのアンプ,スピーカー
- (2) シンセサイザーの音を演出する付加装置
4章 シンセサイザーの多重録音
- 手近にできる多重録音
- (1) 多重録音の楽しさ
- (2) 多重録音を始めよう
- (3) 多重録音に使えるカセットテレコ
- (4) カセットテレコを使った多重録音
- (5) ステレオオープンデッキ1台を使った多重録音
- 多重録音の基本テクニック
- (1) 「ダビング・ロス」という多重録音の宿敵
- (2) 最良の録音状態とは
- (3) 録音レベルの監視役VUメーター
- 多重録音の大道具,小道具
- (1) 改めて録音機を選ぶならばオープンリール型
- (2) 多重録音用としてふさわしい4チャンネルデッキ
- (3) 4チャンネルデッキを使った多重録音
- (4) いろいろなミキサー
- (5) 付加装置を使って音の演出のすすめ
- (6) テープの良し悪しも作品への影響あり
- (7) 録音機のクリーニングセットも重要な小道具
- (8) 接続コードやプラグアダプターの準備も周到に
- (9) シンセサイザー以外の音源
- 多重録音の実際
- (1) 多重録音の手順
- (2) 録音のプログラムづくり
- (3) カウント音の使用
- (4) シンセサイザーの機能を応用した録音レベルの設定
- (5) テープスピードを応用した録音
- (6) 抑揚の変化をつける方法
- (7) 作品として完成させるための編集作業
5章 シンセサイザーの選択,操作,手入れのポイント
- シンセサイザー選択のポイント
- (1) どのくらい機能が必要か?
- (2) モデルによって機能が違う場合もある
- (3) グレードアップの考慮
- シンセサイザー操作のポイント
- (1) 音が出ない?
- (2) こんな音を作るはずではなかった!
- (3) ノイズを拾う設置場所
- (4) 接続コードの知識
- シンセサイザー手入れのポイント
- (1) 異常な温度,湿度は避けよう
- (2) 楽器の日光浴や溶剤によるクリーニングはタブー
- (3) 生兵法は大怪我の元
|
|
前半は、軽い概論と、アナログシンセの音づくりが中心です。
題材に取り上げられているのは、
ROLANDのSYSTEM100のメインモジュールですが、機種名は明示されていません。
各機能モジュールの説明をしながら、音づくりを進めていくスタイルなので、
「体で覚える」派の方にはわかりやすいかもしれません。パッチシートもいくつか掲載されています。
後半は、周辺機器と、多重録音の進め方です。当時の、アマチュアの(夢の)製作法の典型といったところです。
現在ならば、ハードディスク・レコーダー一台でそれ以上のことができますが、当時、
8トラック録音は数十万円コース。
4トラックでも20万円以上のデッキと同額程度の2trマスターデッキが必要でした。
ですから、この本に軽く書かれている環境を持つのは、本当に、夢のようなことだったのです。
(2005/03/23)
|
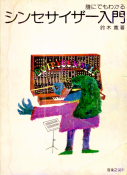 |
誰にでもわかる
シンセサイザー入門
|
| 鈴木寛 | 音楽之友社 | --- | 1977
|
- 簡単な音響学
- 振動
- 周波数(Frequency)
- 強さ(Intensity)
- 音の合成
- 音色
- フーリエ理論/エンベロープ(Envelope)/ほんとうの音色
- 共鳴
- マスキング効果
- 音の方向
- うなりとモジュレーション
- シンセサイザーの原理と機能
- シンセサイザーとは
- シンセサイザーのシステム
- システムの成り立ち/直列と並列(SeriesとParallel)
- 信号(Signal)の種類
- 音声信号(Audio Signal)/制御信号(Control Signal)
- 倍音分析(Spectrum)
- 波形(Wave Form)
- フィルター(Filter)
- 固定フィルター(Fixed-Filter)/VCF(LPF)
- アンプリファイアー(Amplifier)
- 制御装置(Controllers)
- 鍵盤(Keyboard)/リニア・コントローラー(Linear Controller)/シーケンサー(Sequencer)/ADCとDAC/サンプルアンドホールド(S&H)/メモリー・コントローラー
- いろいろな追加装置
- シュミット・トリガー、インタフェース/
エンベロープ・フォロワー/
フリケンシー・フォロワー/
リング・モジュレーター/
フリケンシー・シフター/
フェイズ・シフター/
スプリンガー、ハーモナイザー/
ジョイスティック/
ミキサー/
残響装置/
人声の合成/
ボコーダー
- いろいろなシンセサイザー
- Moog Music inc./
Buchla &Amp; Associates/
ARP Instruments Inc./
Electronic Music Studio,Ltd.(EMS)/
日本楽器製造株式会社(YAMAHA)/
ローランド株式会社/
京王技研工業株式会社/
その他のメーカー
- 実技編
- 第1課 ジェネレーター
- レッスン1 ブロックダイヤグラムの見方
- レッスン2 VCOの操作
- レッスン3 パルス・ワイズ
- レッスン4 フリーケンシー・モジュレーション
- レッスン5 同期
- レッスン6 複数のVCOのチューニング
- レッスン7 ノイズ・ジェネレーター
- 第2課 プロセッサー
- レッスン1 VCF
- レッスン2 VCFの発振
- レッスン3 ハイ・パス・フィルター
- VCFに関するまとめ
- レッスン4 リング・モジュレーション
- レッスン5 VCA
- 第3課 制御装置(Controllers)
- レッスン1 エンベロープ・ジェネレーター
- レッスン2 LFO
- レッスン3 サンプルアンドホールド(S&H)
- レッスン4 鍵盤(Keyboard)
- レッスン5 シーケンサー(Sequencer)
- 応用編
- 第1課 音色作り
- レッスン1 ほしい音を作る
- レッスン2 サウンドチャート利用
- レッスン3 プリセットの利用
- 第2課 メロディーの演奏
- 第3課 電子スタジオ
- レッスン1 多重録音の技術
- レッスン2 トラックダウンとミキシング
- 第4課 合奏(アンサンブル)
- 第5課 調整、修理
- これからのシンセサイザーとその利用
|
|
教科書的な内容のアナログシンセサイザーの本です。
「使う」ということに重点を置いて、当時としては、総括的に、かつ、
実際的に書かれた本でした。
現在、読み返すと、いくつかの内容の不備や偏りが気になりますが、
それを差し引いて、とてもよい本だと思います。
一時期、シンセの入門書というといつもこの本を薦めていました。
(2005/03/23)
|
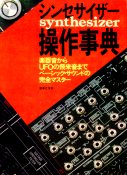 |
シンセサイザー操作事典
楽器音からUFOの飛来音までベーシック・サウンドの完全マスター
|
山室紘一・安保茂・杉原和司・
池田穣・牛久久男 | 音楽之友社 | --- | 1982
|
■シンセサイザーの原理と基礎操作
- PART1 シンセサイザーの原理
- 音の正体
- シンセサイザーの三要素
- VCOの機能
- VCFの機能
- VCAの機能
- EGの機能
- NGの機能
- リング・モジュレーターの機能
- LFOの機能
- キーボードの機能
- PART2 シンセサイザーの構成と基礎操作
- ブロック・ダイヤグラム
- コントロール信号のはたらき
- 基本セッティング
- パネル・セッティング
- PART3 シンセサイザーによる楽器音の合成
- シンセサイザーによるシミュレーション
- 波形を選ぶ
- VCFの設定
- EGの設定
- 楽器に応じた表現
- PART4 シンセサイザーの周辺機器と使い方
- ベスト・セラー機3モデルの機能と特徴
■シンセサイザー操作事典
- <木管楽器>
- ピッコロ
- フルート
- クラリネット
- オーボエ
- イングリッシュ・ホルン
- ファゴット
- <金管楽器>
- サクソフォーン
- トランペット
- フリューグル・ホルン
- トロンボーン
- バス・トロンボーン
- チューバ
- ホルン
- <弦楽器>
- ヴァイオリン
- ヴィオラ
- チェロ
- コントラバス
- ストリングス
- <鍵盤楽器>
- エレクトリック・ピアノ
- ハモンドオルガン
- パイプオルガン
- チェンバロ
- クラビネット
- <撥弦楽器>
- エレクトリック・ギター
- ウッド・ベース
- エレクトリック・ベース
- マンドリン
- <打楽器>
- グロッケン/チェレスタ
- ヴィブラフォン
- シロフォン/マリンバ
- スネア・ドラム
- バス・ドラム
- シンセ・ドラム
- ティンパニー
- トライアングル
- クラベス
- <特殊楽器>
- アコーディオン
- ハーモニカ
- 口笛/リコーダー
- 人声
- <自然音>
- <人工音>
- 救急車のサイレン
- ヘリコプター
- ゲーム・マシーン
- 蒸気機関車のドラフト音
- <想像音>
|
|
この本だけは、アナログシンセサイザーの本としては、新しい本です。
内容は、要するにパッチシート集。
機種として三機種、
- Roland SH-2
- Korg MS-20
- Yamaha CS-10
が取り上げれていて、全部の音色に対して3機種すべてのパッチシートがあります。
音色作りのコンセプト、機種別の解説も書かれており、特に、
機種ごとの機能の違いに対応する変更点など、読んで楽しいものです。
音づくり自体は、標準的な方法のものばかりです。
本の最初のほうには、アナログシンセとその周辺に関して、大雑把な解説がついています。
(2005/03/23)
|
 |
シンセサイザー●その歴史と理論の実際
|
Herbert A. Deutsch 著
梯郁太郎 訳 | パイパーズ | --- | 1979
|
第1章-近代以降の音楽
- 印象主義:色彩としてのサウンドの発見
- 12音音楽と無調音楽:オーガニゼーションとインスピレーション
- ダダイズム:芸術における理論の崩壊
- 沈黙とソノリティ:音楽における時間の再定義
- アレアトリーとインプロヴァイゼイション:偶然の論理と不確実性
- 結論/折衷主義:全体は部分を合わせたものより偉大である
第2章-電子音楽小史
- 第二次世界大戦以前
- テープ音楽とミュージック・コンクレート
- 現代の電子音楽:その第一期
- 現代の電子音楽:その第二期
- 個人的回想:1963~1965
- 現代の電子音楽:その第三期
第3章-楽器としてのテープ・レコーダー
- 録音テープ
- テープ・ヘッドの位置
- テープの反転
- テープ速度の変化
- スプライシング
- テープ・ループ
- サウンド・オン・サウンド
- 信号対雑音比(SN比)
- テープヘッド・エコー
- テープ・スタジオのセットアップ
- 空間的な音の位置
- マイクロフォン
第4章-電子的な音の合成
- 基礎
- スピーカー
- 発振器と波形
- アンプリファイアー
第5章-シンセサイザー(1)
- オーディオ発振器
- コントロール・システム
- 周波数変調
- 発振器ミキサー
- 電圧制御アンプリファイアー
- 振幅変調
第6章-シンセサイザー(2)
- ロウ・パス・フィルター
- ハイ・パス・フィルター
- バンド・パス・フィルター
- バンド除去フィルター
- 固定フィルター群
- プログラム・イコライザー
- 電圧制御フィルター
- リジェネレーション
- ランダム信号発生器
- 残響ユニット
第7章-シンセサイザー(3)
- リング変調
- サンプル・アンド・ホールド
- アナログ・シーケンサー
- デジタル・シーケンサー
- コンピューター
- まとめ
付録:スタジオにて
- (第3章より)
- 実習1:テープの速度と方向を使った実験
- 実習2:複合サウンドの制作
- 実習3:テープ・ループ
- 実習4:サウンド・オン・サウンド
- 実習5:テープ・エコー
- 実習6:ミュージック・コンクレート
- (第4、5章より)
- 実習1:バッハのコーラルを用いて(第一版)
- 実習2:バッハのコーラルを用いて(第二版)
- 実習3:“Electrophunk in A”
|
|
この本は、
テープレコーダーとシンセサイザーによるミュージック・コンクレート講座といった内容です。
クラシックの現代音楽(この言い方も変ですが)の流れから見て書かれているようで、
まるで、XX大学「現代音楽の制作(テープとシンセによる)」の教科書風。
前半が、扱う音楽の概観と、テープの技法。後半が、シンセの解説となっています。
テープの技法は、スプライシング(切り繋ぎ)、テープ・ループなどで、なかなか、
貴重なものだと思います。
後半のシンセの機能解説も、程よい加減です。といって、それほど詳しいわけではありません。
最後に、実習例が譜面付で書かれています。
このあたりも、まるで、学校の実習教科書のようで面白いところです。
(2005/03/23)
|
 |
パソコンミュージック入門
|
| 山口公典・加藤博万 | オーム社 | --- | 1985
|
序章 主要用語の説明
- [1]音源用語
- [2]数値用語
- [3]データ通信用語
- [4]コンピュータ用語
- [5]ソフトウェア用語
1章 電子音楽の基礎
- 1-1 電子楽器の構成要素
- 1-2 代表的な音源
- [1]電圧制御方式による音源
- [2]ディジタル音源
- 1-3 音源コントロール
- [1]音色パラメータのコントロール
- [2]音源のスタート,ストップのコントロール
- 1-4 楽器のネットワーク
2章 パソコンの基礎
- 2-1 パソコンのアーキテクチャ
- [1]CPU
- [2]メモリ
- [3]パソコン音源
- [4]タイマ機能と割込み
- [5]シリアルコミュニケーションインタフェース
- [6]その他の要素
- 2-2 パソコンミュージックソフトウェア
- [1]MBIOS(ミュージックBIOS)
- [2]音色パラメータのアクセスプログラム
- [3]コンポーザプログラム(音楽用ワードプロセッサ)
- [4]ミュージック言語
3章 パソコンミュージックハードウェアの実際
- 3-1 MSXの標準ハードウェア
- [1]全体の構成
- [2]I/Oマップ
- [3]割込み
- [4]メモリスロット
- [5]ディスクサポート
- 3-2 CXシリーズコンピュータに特有なハードウェア
- [1]CXのメモリ配置
- [2]FMシンセサイザカートリッジ(SFGシリーズ)
- [3]FM音源の性能
4章 パソコンミュージックソフトウェアの実際
- 4-1 ボイシングプログラム
- [1]オペレータ結線(アルゴリズム)
- [2]オペレータの周波数制御(F,IF,DT)
- [3]エンベロープ(ADSRR,Ks,Kd,Rk,Vs,Aj)
- [4]LFO(LFO,Syc,Wf,Spd,Amd,Pmd,Ams,Pms)
- [5]その他(Tr,LR)
- [6]音色データの使われ方
- 4-2 ミュージックマクロ
- [1]ミュージックマクロの構造
- [2]楽器の定義
- [3]楽器の属性の変更
- [4]演奏入力(トラック)
- [5]演奏
- [6]演奏とBASIC実行の同期合わせ
- [7]ダブルバッファリング
- [8]複数の楽器を同期する方法
- [9]その他のコマンド
- [10]楽譜リスト(P-リスト)
- [11]ミュージックプログラム解説
5章 コンピュータミュージック一般
- 5-1 MUSIC V
- 5-2 現在のミュージック言語
- 5-3 これからのコンピュータミュージックソフトウェア
- 5-4 コンピュータミュージックハードウェア
付録
- 付-1 MIDIの概要
- 付-2 ハードウェア構成
- 付-3 データフォーマット
- 付-4 MIDIインタフェースソフトの考え方
- 付-5 MIDIシステムの構成
|
|
昔のMSXパソコンにYAMAHAのSFG(FM音源+MIDIインタフェース)を装着した、
ミュージックコンピュータを対象に、ソフト、ハードの解説を行っています。
また、最後の章では、汎用的な音楽生成ソフトウェアについて、わかりやすい説明もあります。
現時点では、さすがに、MSXのハードの説明に興味のある方は少ないでしょうが、
MIDIの説明、FM音源(SFGは4OPですが)の説明などは、今も、十分に通用する内容です。
(2005/03/23)
|
 |
DXシンセサイザーで学ぶ
FM理論と応用
|
| ジョン・チョウニング/デビッド・ブリストウ | 財団法人ヤマハ音楽振興会 | 4-636-20835-8 | 1986
|
- 概論
- 基本的な考え方
- FMとは何か
- 単純FM-理論編
- 単純FM-実践編
- 複合FM
- FMの応用
付録
- 対数スケール表示と“音程周波数”
- 変調指数 vs. 出力レベルによる“X”シリーズ各機種の比較
- ベッセル関数のグラフ
- ベッセル関数表
- 参考文献
- 基本用語集
- DX7のサンプリング周波数
|
|
YAMAHAのFM音源で音づくりをする人ならば、たぶん、持っている本です。
DX-7を横に置き、実際に音を出しながら読み進めていきます。
学者さんが書いた本ですから、硬い内容なのですが、
理解できるところだけをつまみ食いをしても、楽しめます。
実際の音づくりに役立つかといえば、誰にでも役に立つというわけではありません。
理屈っぽく考えて音を作るときの、基本知識になるものだと思います。
とはいえ、「FM音源の考案者」といわれる人の書いた本なので、持っていたい本なのです。
(2005/03/23)
|
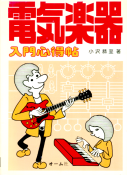 |
電気楽器
入門心得帖
|
| 小沢恭至 | オーム社 | --- | 1979
|
第1章 電気楽器を始める人のために
- 電気楽器の楽しい世界
- 各種の電気楽器
- ギターとベース
/電子オルガン
/ハモンドオルガン
/シンセサイザー
/ディジタルシンセサイザー
/その他の電気・電子楽器
- アコースティックな楽器
第2章 電気ギターの基礎知識
- ギター各部の名称とその役割
- アーチトップ
/エフ孔
/カッタウェイ
/ブリッジと音の伸び
/弦長とスケール
/フレットとセント
/ストリングスゲージ
/トラスロッド
/ネックのそり調整
/ペグ
/スチールボックス
/ギター用材
- 電気ギターのピックアップと内部回路
- ハムバッキング型ピックアップ
/トレブルピックアップ
/ピックアップの位相
/ピックアップの出力
/トグルスイッチとノブ
/内部配線例
/ギター内部用ブライト回路
/ギター,ベース用減衰型イコライザ
/トーンセレクタ
- 現代のギターサウンド
- ディストーションサウンド
/ウーマントーン
/ギターの音の伸び
/チョーキング
- ギターの選び方
第3章 電気楽器ユーザーのための基礎知識
- 音の知識
- 音と風
/音波と電波
/倍音
/度
/調性
/メジャーとマイナー
/平均率音階
/自然倍音
- 電気の知識
- アース
/ヘルツ
/リアクタンス
/インピーダンス
/抵抗とコイルとコンデンサの機能
/オームの法則
/デシベル
- 種々の電気・音響特性
- SN比
/リニアリティ
/f特
/指向特性
/ダイナミックレンジ
/カットオフ周波数
/位相
- 電子部品の知識
- 半導体・導体・絶縁体
/半導体の名称
/素子の極
/MOS
- 記号と規格
- 回路図の記号
/カラーコード
/ISO
/JIS
/DIN
/BTS
第4章 電気楽器用アンプの考え方
- アンプの基礎知識
- インプットとアウトプット
/アンプの出力
/入出力レベル
/インピーダンスマッチング
- アンプ回路の構成
- エミッタ・フォロワ
/バッファアンプ
/コンプリメンタリ
/A級・B級
/可変抵抗器
/アンプの電源
/グランドスイッチ
- 各種のアンプ
- ギターアンプ
/小型ギターアンプ回路図
/ベースアンプ
/オルガン,シンセサイザー用アンプ
第5章 上手に効果装置を使いこなすために
- 各種の効果装置
- エクスプレッションコントロール
/エコーチェンバ
/ディストーション
/ワウ
/フェイザー
/フランジャー
/コーラス
/コンプレッサ
/イコライザ
/ドライバ
/オクターブシフター
/ステレオボックス
/トーキングモジュレーター
/ユニバーサルエフェクタ
/オーバードライブ
/フィードバック
- ノイズゲートと各種のフィルタ
- ノイズゲート
/ハイパスフィルタ
/ローパスフィルタ
/バンドパスフィルタ
/バンドリジェクトフィルタ
/パッシブフィルタとアクティブフィルタ
- さらに効果装置をうまく使うために
第6章 スピーカの本質に迫る
- スピーカの基礎知識
- スピーカに関する記号と口径
/磁石
/スピーカ用マグネットの大きさ
/ダンピングファクタ
/負荷インピーダンスと出力
/出力音圧レベル
/音響出力
/ランバーコア材
- スピーカの諸特性
- シングルコーンスピーカの特性
/ピストン振動域
/スピーカの指向特性
/低音特性
/トゥイータの入力
/スピーカのカットオフ周波数
- スピーカシステムを使いこなすために
- スピーカの種類と使用方法
/ツインドライブ方式
/ドロンコーン
/ASW
/TQWT
/スピーカシステムの自作
/中音用ホーンの自作
/密閉型キャビネット
/ディバイディングネットワーク
/チャネルディバイダ
/アッテネータ
/簡単な実用アッテネータ
第7章 PAと音場作り
- PAの基礎知識
- ミクサーの基礎知識
- ミクサー
/ミクサーの各部の名称
/インプットセレクタ
/トーンコントロール
/パンポット
/自作できる簡単なミクサー
- PA用スピーカの基礎知識
- PA用スピーカ
/PA用スピーカの配置
/スピーカの多数個駆動
/複数個スピーカの接続
/並列接続
- 音場作り
- 音場作りの工夫
/録音と再生の音場
/残響時間の決め方
/整音作業
/暗騒音
/マスキング
/吸音
/しゃ音
/野外の音場
一口メモ
- 楽器のピッチ調整
- 故障修理の着目点
- スペック
- 楽器本体のスペック
- そろえておきたい工具(その1)
- 揃えておきたい工具(その2)
|
|
これは、シンセサイザーの本ではなく、電気楽器の本です。
といっても、楽器そのものでなく、その周辺の話が、実用的にまとめられています。
アンプ、エフェクタ、スピーカー、ミキサー、PAなど、結局、
シンセサイザーもお世話になることが多いのですから、当然、シンセにも適用できるわけです。
内容は、時代相応に古いのですが、役に立つ知識満載といったところです。
(2005/03/23)
|